Hola~オラ~
こんにちは!ハポネコです。
先日、メキシコの助成金制度 PECDA(Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico) の審査員を務める機会がありました。
アーティスト支援制度に関わる裏側を実際に体験してみると、日本との違いや、支払いに必要な手続きのリアルな側面も見えてきました。今回はその体験をまとめてみたいと思います。
どうぞお気軽に御覧ください。
1. PECDAとは?メキシコ全州に広がるアーティスト支援制度
PECDAはメキシコの文化省と各州の文化機関が共同で運営する、芸術家や文化マネージャーを支援する制度です。
特徴的なのは、全国32州すべてで実施されていること。美術、舞台、文学、音楽、映像、研究など、幅広い分野のプロジェクトが対象になります。
「地方に住んでいるから応募できない」ということはなく、どの州のアーティストにもチャンスがある仕組みになっているのがとても大きなポイントだと感じました。
各州によって募集時期に違いがあり、公募は5月くらいからで結果発表は7~8月。実施は11月から8ヶ月間になります。
10代、20~30代、35才以上とキャリアによって募集が分かれているのも特徴です。

2. 審査員として関わる仕事の流れと役割
審査員の仕事は、まずオンラインプラットフォーム「Fonca en línea」を通して提出された申請書類を確認することから始まります。
その後、招集された審査会で討議を重ね、採択プロジェクトを決定していきます。
今回は52名のプロジェクトから審査によって10名を選びました。
審査員は3名で各自点数つけて、どのプロジェクトが推せるのか?投票を記入した用紙を提出。
その後オンライン会議で話し合いながら決定です。
メキシコは汚職や不正も多い印象なんですが、PECDAに関しては公平でシステム的にもしっかりしています。
評価のポイントは、作品や企画の芸術的な質だけでなく、実現可能性や地域社会への波及効果も重視されるのが特徴的でした。
ハポネコの印象としては特に地域性が重視されていた印象です。やはり皆様の大切な税金をどう活用するのか?アイデア勝負ですね。
作家の未来に直結する判断をするので責任は重いのですが、同時にチアパスとは違う地域の多様な分野の提案に触れることで、自分自身の活動にとっても大きな学びになりました。
メキシコって広くて多様なのね….
よいプロジェクトは文章から企画の空気や意図が自然に伝わってきて、すごく完成度が高いなと感じました。
3. 日本の助成金制度との違い:地方分権と手厚さの比較
日本の芸術助成は、文化庁や芸術文化振興基金が中心で、全国的な制度としてはどうしても「中央集権型」になりがちです。
自治体の助成もありますが、地域によって規模や条件に大きな差があるのが実情です。
一方、メキシコのPECDAは 「国+州の協働」 という形をとっているため、地方に住むアーティストでも平等に応募できる仕組みが整っています。
また、ジャンルの幅広さや、研究者や文化マネージャーも対象になる点も、日本より手厚いと感じる部分でした。
審査員にも地元と外部の専門家が組み合わされるため、地域性と専門性の両面からプロジェクトが評価されるのも興味深い点です。
さらに背景として、メキシコでは20世紀初頭の壁画運動以来、芸術が国家事業として教育や社会に組み込まれ、アーティストが社会的にリスペクトされる基盤があります。
一方、日本ではマンガやアニメを含む大衆文化が「アート」として広がりを持つ一方で、境界が曖昧になり、支援制度としては玉石混交になりがちな面もあると感じます。
4. 報酬を受け取るための手続きと必要書類
審査員としての仕事を終えると、報酬の支払い手続きが始まります。ここで必要なのがメキシコならではの書類です。
-
Constancia de Situación Fiscal(税務状況証明):RFCと税務状況を示す書類、SATで発行。
-
CURP(個人識別コード)
- 住所証明(電気支払いなどのレシート)
-
銀行口座情報(CLABE interbancaria)
-
身分証明書(INEやパスポート)
-
場合によっては e.firma(電子署名)
これらをPDFで提出するのが一般的で、準備が遅れると支払いも後ろ倒しになってしまいます。
最初は戸惑いましたが、一度流れを経験してしまえば次からはスムーズに対応できそうです。
ハポネコは税務状況証明を請求されたのが初めてで、少しあせったのですがSATへいくと10分くらいで印刷してもらえました。
アーティストとしても登録が可能で、その場合は作品が売れなくとも毎月報告しなければなりませぬ。
おわりに
PECDAの審査員として関わってみて、日本の助成制度と比べると「地方分権型で手厚い支援」という違いを強く感じました。
同時に、アートを支える仕組みは作品そのものと同じくらい重要であり、その裏方の手続きまで含めて制度が機能していることを実感しました。
これからも、ハポネコ自身の制作だけでなく、こうした制度の一部に関わる経験を続けていきたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
また別の記事でもお会いしましょう。
Nos Vemos またね~
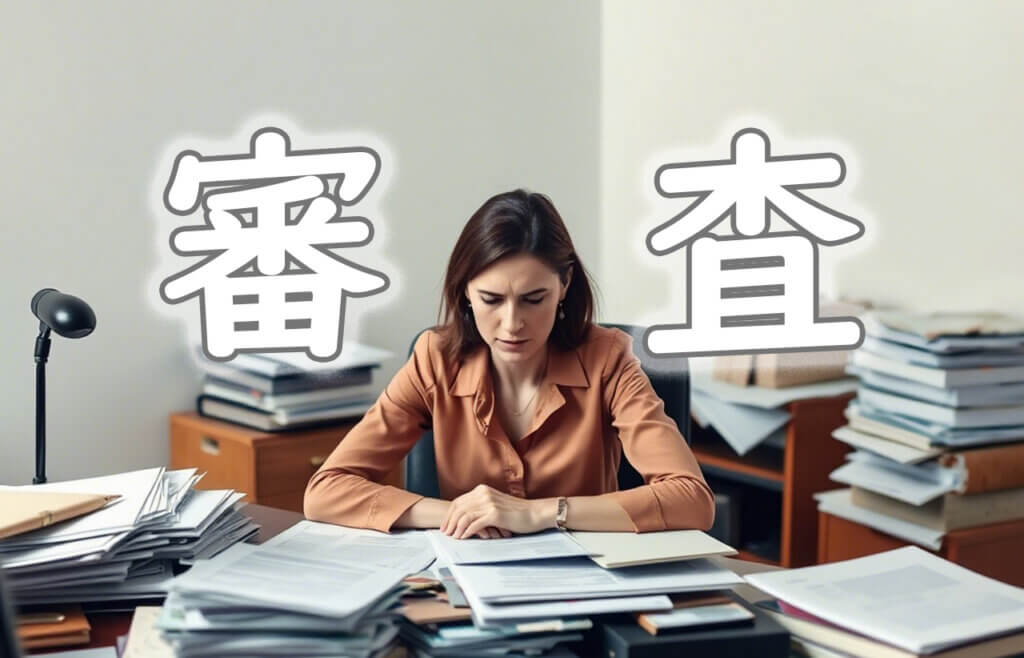
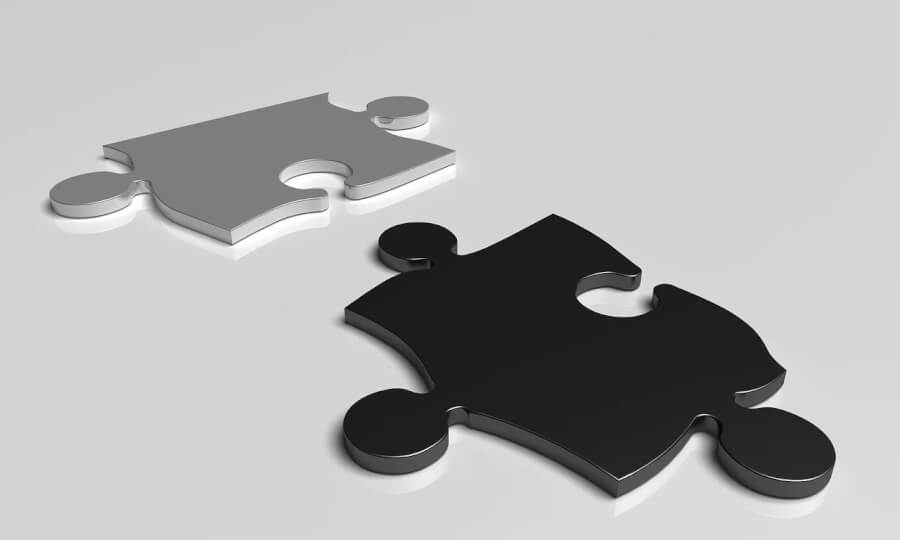


コメントを残す